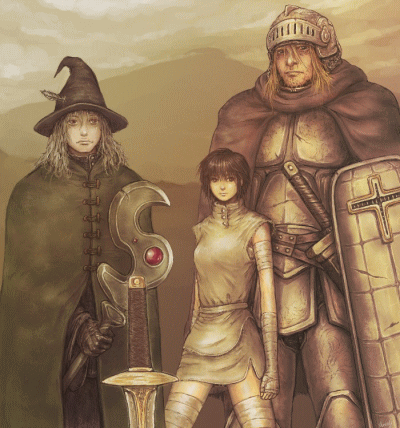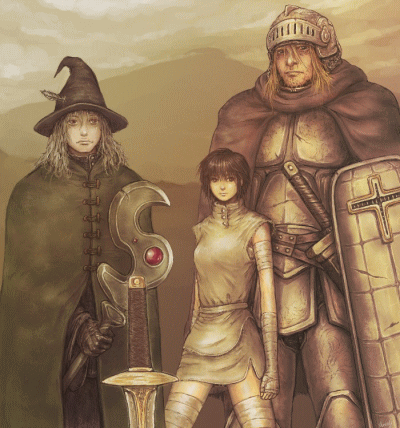勇者の報酬
■長さ■
50枚(四百字詰め原稿用紙換算)
■あらすじ■
勇者率いる一行は、魔王を倒した。世界に光は戻った、しかし……。魔王打倒後、生き残った三人に襲いかかる真の恐怖。欲望、嫉妬、打算、裏切りが渦巻く洞窟内で、生き残るは誰か?
勇者の報酬
焚き火の炎がパチパチとはぜ、細く、白い煙が上がる。
細いながらも鍛え抜かれた上腕で、両膝を抱え込むように座っている少女が、ふいにそう漏らした。
「それは……、知りませんでした」
色褪せた濃緑のローブをまとった細身の青年は、軽く眉根を寄せた。
少女と青年、二人は焚き火を挟んで向かい合い、先ほどからまんじりともしなかった。
空気が乾いている。
少女が、乾燥しはじめた上唇をペロリと舐めた。
ここは洞窟の中。
青年の右手に見える出口から、時折り冷たい風が吹き込む。
冬の夜。外は満天の星空。
とはいえ、洞窟の中から星空は見えはしないのだが。
染色していない麻の上着を、腰紐で軽く縛っているだけの少女は、ヒザを抱いたまま俯き加減につづけた。
「生きるためなら何でもしてきた。人殺しさえも厭わなかった。何も感じなかった……」
少女の独白に、青年は口を挟まなかった。
「だからこそ」
少女はつと、語気を強めた。
「私が生きるために殺した人間、私を導いてくれた修道院、それに……、死んだ勇者のために、私は生き抜かねばならない」
「仰るとおりです」
青年は静かに相槌を打った。
「あなたは聡明な方だ。生きるとはどういうことなのか、よく理解してらっしゃる」
撫でるような青年の声。
毒蛇がチロチロと舌を出しているようだった。
「では、我々が生きるための具体的な方法を、これから打ち合わせることにしましょう。よろしいですね?」
少女はコクリと頷いた。
「打ち合わせるなど」
少女の端正な口元が、少しだけ、嫌な感じに歪んだ。
「何も面倒なことは必要ない。私の体術、あなたの魔法。この二つが組み合わされば、いかな戦士といえども……」
少女が、ふと口をつぐんだ。
洞窟の入口で、人の気配がしたのだ。
青年も同じく押し黙った。
世界に光は戻った。
しかし、自分たちが超えねばならぬ闇は、まだまだ濃く、深かった。
時計の針を、少しだけ戻す。
“デビル・マウンテン”と呼ばれる山があった。
世界中の人間を恐怖のどん底に叩き込んだ魔王が棲む山である。
いや、『魔王が棲んでいた山』というほうが、今は正しい。
たった今、人間界の希望の星、選ばれた勇者率いる一行が、苦難の旅の末、見事、魔王を打ち倒したからだ。
世界に光が戻った。
デビル・マウンテンの麓の洞窟。
そこへ、荒い息を吐きながら飛び込んだ三人がいた。
「ハァハァ、どうだ、追っ手の怪物どもは?」
洞窟内で片膝を付き、巨体を激しく上下させて息をするのは、鈍色の甲冑を着込んだ金髪の男だった。
繊細な象嵌が彫りこまれた見事な鎧である。
「とりあえずは大丈夫のようだ」
洞窟の入口で空を見上げていた、軽装の少女が答えた。
端正ながらも精悍な顔立ちに、短い黒髪が映える。
麻の上下に、サンダル履き。
こちらも息を乱してはいたものの、まだ余力が感じられる。
「私はしばらく外で見回りをしている。お前たちは休んでいろ」
「あ、ありがとう、ハァハァ、ございます」
息も絶え絶えに答えたのは、すでに地面に伏して一歩も動けない、濃緑のローブをまとった色白な青年だった。
汗のにじむ額に、灰色の髪が貼りついている。
三人はつい先刻、魔王を倒した勇者の一行だった。
「私たちは、とうとう、ハァハァ、ついに、やったんですね」
苦しげに呼吸しながらも、ローブの青年の瞳はキラキラと輝いていた。
「そうだ。俺たちは、ハァハァ、やったんだ。あの魔王を討ち倒したんだ」
荒い息をつきながら、戦士が相槌を打つ。
二人の表情は誇りに満ちていた。
「そして私たちが、世界の光を取り戻した」
少女がニコリと、歳相応の愛くるしい笑顔で二人に頷いた。
「しかし、喜ぶのは魔王軍残党の追っ手を振り切ってからだ」
少女が表情を引き締めた。
「そうですね。しかし、ここはひと呼吸入れましょう。私はもう、体が、動かない」
「そうだな。俺も少し休まねば、剣を持つこともできん」
青年は体力不足のため、戦士は重装備のため、もう歩くことさえ困難になっていた。
ひとり体力に余裕のある少女が、見回りのため洞窟を出かかった時、ふと呟いた。
「勇者のことだけが……」
少女の言葉が耳に入り、青年と戦士の表情にサッと影が落ちた。
「勇者殿のことは……、残念でした。私の力が足りなかったばかりに……」
青年が痛恨の表情を浮かべる。
「いや、俺だ。俺にもっと力があれば……」
戦士は俯き加減になり、歯を食いしばった。
固く瞑られた両目から、汗ともに熱い涙が滴り落ちる。
少女は無言で視線を落とすと、細い背中を震わせて洞窟の外へ姿を消した。
三人は勇者の仲間だった。
勇者は、三人の若さゆえの無限の可能性にかけて、彼らを仲間とした。
勇者の見立てどおり、三人は戦いの中でメキメキ実力を伸ばした。
人間界を苦しめる悪の魔王を倒し、平和を取り戻す。
光り輝くばかりの使命感に、四人は燃えていた。
どんな苦しみも悲しみも、自分たちが世界を救うのだ、という熱い想いを妨げることはできなかった。
そしてとうとう、四人は魔王を打ち倒した。
壮絶な戦いだった。
大きな犠牲を払わねばならなかった。
勇者が、禁断の自己犠牲の魔法を唱えて、魔王を打ち倒した。
世界に光を残し、勇者は死んだ。
崩れ落ちる魔王の宮殿から、三人は命からがら脱出した。
三人とも、勇者の英雄的行為に、走りながらも涙が止まらなかった。
ともすれば感動で、足が動かなくなりそうだった。
あれこそ世界を救う勇者たる証だった。
勇者は死んだ。
しかし、その高潔な行為は永遠だ。
共に血と汗と涙を流した勇者の最後の姿が、三人の脳裏に焼きついていた。
少女が、見回りのため外へ出た。
洞窟内は、灰色髪の青年と金髪の戦士、二人になった。
呼吸が楽になってきた青年は壁に背をもたせかけ、膝を抱えてボンヤリと考える。
自分たちは魔王は倒した。世界に光は戻った。
残念ながら勇者は還らぬ人となったものの、世界は自分たちを英雄として迎えてくれるだろう。
しかし……。
狡兎死して走狗煮らる
そんな諺が、青年の脳裏をよぎる。
熱狂が収まり、平和が当たり前のものとなれば、自分たちはどうなるだろう。
尊敬や羨望は、やがて嫉妬や妄執に変わるかもしれない。
猜疑心の強い各国の王たちは、なおさら自分たちを煙たがるだろう。
平和を求める勇者の私心なき行動すら、王たちはおのおの政治的謀略に使い、何度も足を引っ張ったのだ。
世界中の民衆の圧倒的支持を受け、絶対のカリスマを誇った勇者が存命ならまだしも……。
自分たちだけでは、運命はどうなるかわからない。
今度は自分たちが命を狙われる立場にさえ……。
洞窟の真ん中に、鈍い光を放つ魔王金貨が十枚。
魔王城が崩壊する中、少女がなんとか奪い取ってきた、魔王の宝だった。
魔界の技術で精錬されたその金貨は、人間界では一枚で人ひとりが十年遊んで暮らせるだけの価値を持つ。
金銀財宝が煌くばかりだった魔王の宮殿から持ち出せたのはそれだけだった。
この報酬を、自分たちは三人で分ける。
青年は考える。
自分たちはまだ若い。
魔王金貨を三等分しては、身を隠して死ぬまで遊んで暮らせるほどではない。
青年は、濃緑のローブの中で、そっと魔法の杖を握りしめた。
目の前、大の字で横になっている戦士を、炎の魔法で灰にしてやろうか、と。
だがそれは、と思いとどまる。
青年は、杖から手を離し親指の爪を噛んだ。
魔王城攻略は、激戦に次ぐ激戦だった。
自分の魔力は今、ほぼ底を尽いている。
戦士を一瞬で焼き尽くす炎はまだ撃てる。
ただし、一発が限界だろう。
魔力を加減して撃つことはできるが、それでは戦士の反撃を食らってしまう。
たとえ瀕死の状態でも、なりふり構わず来られれば、自分もただでは済むまい。
そこへ、少女が帰ってくればどうなるか?
灰となった戦士に、半死半生の魔法使い。
洞窟の真ん中には、光り輝く魔王金貨が十枚。
ひとりなら、間違いなく一生遊んで暮らせる額だ。
ダメだ、と魔法使いは頭をふる。
こんな杜撰な計画は、とても実行できない。
勇者と青年たち四人の一行で、自分は常に参謀役だった。
『君の頭脳のおかげで今回も勝てた』
戦いの後の、勇者のいつもそう言ってねぎらってくれた。
難攻不落といわれたデビル・マウンテン攻略の計画を立案し、成功に導いたのも自分だ。
もっとリスクの少ない、確実な作戦を立てねばならない。
それならば、と青年は頭を働かせる。
戦士と力を合わせ、戻ってきた少女に不意打ちを食らわせ、消してしまう。
そのほうが、ずっと成功率は高い。
戦士にとってもけっして悪い話ではない。
魔王金貨を五枚づつ分けても、十分暮らしていける。
この計画に賛成するに違いない。
青年は、おのれの智略家としての深謀遠慮に、ぞくぞくするような快感を覚えた。
灰色の髪を軽く掻きあげ、青年は呟くように低い声で切り出した。
「目の前の金貨を、二人で山分けする。そんな物騒な考えが浮かんでしまうのは、魔王の悪の波動を浴びた影響でしょうかね……」
反対された時の用心のため、曖昧で冗談めかした口調だった。
戦士は目を瞑ったまま、こちらも独り言のように呟いた。
「不思議なものだな。俺もいま、同じことを考えていた……」
拒絶の響きはない。
青年は心中、ホッと息をついた。
「私たちはこれまでも、そしてまさにこれからも、協力できそうですね」
「うむ、我々二人が金貨を山分けするため、邪魔な者をひとり消す。その具体的な方法だが……」
戦士がノソリと上体を起こした時、洞窟の入口で足音がした。
見回りに出ていた少女が戻ってきたのだ。
戦士は慌てて口をつぐむ。
「少しは回復したか? 悪いが見回りを代わってくれないか」
間の悪い時に戻ってくる。
魔法使いと戦士は、心の中で舌打ちした。
「では、私が行きましょう」
ここでグズグズしては怪しまれると思い、魔法使いの青年が腰をあげた。
「では、また後で」
魔法使いは、戦士に意味ありげな視線を送ると、洞窟から出て行った。
洞窟の中は、戦士と少女の二人となった。
戦士は落ち着かぬ様子で、何度も寝返りをうった。
たった今、目の前の人間を消す算段をしかかっていたのだ。
とても平静な気持ちではいられない。
少女は見回りから戻ってきた際、ひと抱えの薪を持ってきていた。
火打石を鳴らし、慣れた様子で手際よく火をつけ、焚き火をおこす。
身軽な少女には、特に疲れた様子もなかった。
少女は焚き火の前に腰を降ろすと、背中を向けて横になっている戦士をじっと眺めた。
後ろから少女の視線を感じている戦士は、背中に冷たいものが流れた。
死と隣り合わせの戦場を生き抜いてきた戦士だ。
少女の視線に並々ならぬ気配、はっきり言えば“殺気”が含まれていることがわかる。
先ほどの、魔法使いとの会話を聞かれたのだろうか?
であれば、少女が自分に殺意を持つことに不思議はない。
自分だって、卑劣な裏切りに、怒りで体が震えるだろう。
殺してやりたい、と思うに違いない。
少女が襲い掛かってきたらどうする?
体力はだいぶ回復している。
そうそう遅れはとるまい。
だが、少女は小さな体に底知れぬ体力を秘めている。
鍛え抜かれた体術も使う。
「見回りをしていた途中……」
ふと少女が口を開く。
戦士は心臓が口から飛び出さんばかりに驚いた。ビクリと体が硬直する。
しかし、少女は戦士の狼狽に気付く様子もなく、低い声でつづけた。
「これからのことを考えていた。勇者亡き今、私たちに後ろ盾は無い。私たちに残された確かなものは……」
少女はひと息ついて、焚き火のそばで鈍い光を放っている魔王金貨へ視線を落とした。
「確かなものは金だけだ。その取り分を大きくしようという考えは、どうなのだろう」
「あ、ああ……」
戦士は少女に背中を向けたまま、口の中でモゴモゴと呟いた。
心底驚いた。
まさか魔法使いと同じ提案を、少女からも持ちかけられようとは。
これは大変なことになった、と思うと同時に……。
戦士は胸の奥底から湧き上がる優越感を否定できなかった。
魔法使いか少女。どちらを取るか。
天秤は自分に預けられたのだ。
自分の考えひとつで、他人の未来を踏みにじることができる。
それは麻薬のような快感だった。
貧弱な魔法使いや線の細い体術使いなど、戦いにおいては所詮亜流。
『君のおかげで今回も命拾いしたよ』
戦いの後、いつも勇者はそう言って戦士に感謝した。
戦いの行く末を決定付ける要素は、いつの世でも中核を担う戦士の力量にかかっているのだ。
少女も青年も、自分を必要としている。
だがしかし……。
戦士は、のぼせ上がりそうな自分を諌める。
ここで少女の提案にがっついては、先ほどの魔法使いとの打ち合わせを感づかれてしまうかもしれない。
少女がカマをかけている可能性もあるのだ。
「金を二人で分ければ、もう将来のことを気にせず生きていけるんだぞ」
少女は、いったん口にした言葉は引っ込められないとばかりに、戦士をかきくどきはじめた。
戦士は気のあるようなフリをしつつ、「ああ」「うむ」など曖昧な返事を繰り返す。
やがて少女が苛立ちはじめた。
戦士は、これ以上引き伸ばしては逆効果になる、と判断した。
少女に向かって座りなおす。
「では、魔法使いを消す、具体的な方法を練るとしようか」
その時、洞窟の入口で人の気配がした。
魔法使いの青年が戻ってきたのだ。
戦士は、少女の提案を引き伸ばし過ぎたことを後悔した。
しかし後の祭りである。
「何も異常はありませんでした。申し訳ありませんが、見回りを代わってもらえますか」
「ああ」
戦士は鷹揚に頷くと、重々しく立ち上がった。
「では行ってくる」
戦士は少女と青年の両方に、それぞれ気付かれぬよう、意味ありげな視線を送った。
見回りをしている間、どちらを生かし、どちらを消すのか、ゆっくり考えれば良い。
洞窟から出て行く戦士の背中には、隠しようの無い優越感が漂っていた。
洞窟の中には、少女と青年。
焚き火を挟んで向かい合う二人は、けっして互いの目を見ようとはしなかった。
二人とも、目の前の相手を消す算段をしていたのだ。
とても相手を正視できない。
一刻も早く戦士に戻ってきてもらいたい。
二人の気持ちは、ある意味まったく同じだった。
静かな洞窟。
時折り、パチリとはぜる木の枝が、余計に静寂を際立たせる。
青年はイライラと爪を噛んでいたが、内心の焦りから、つい呟いていた言葉が大きくなった。
「くそっ、戦士のやつ、いったいどこまで見回りにいってるんだ。鈍くさいヤツのことだ。まさか道に迷っているんじゃ……」
あっ、と思ったときには遅かった。
焚き火の向こうから、少女がうろん気な視線で青年を見ていた。
「いっ、いえ」
魔法使いは慌てて取り繕った。
「ちょっと彼のことが心配になりましてね。何しろここはまだ魔王城にほど近い洞窟ですから」
「お前の心配は分かる。アイツは鈍くさいヤツだからな」
少女の棘のある言葉に、魔法使いはオヤッ? っと思った。
そしてすぐピンと来る。
どういう理由か知らないが、少女は戦士を憎んでいるのだ。
考えてみれば、消すのはどちらでもよい。
であれば、人間を動かすもっとも強い要素である“憎悪”を利用しない手はない。
「まったくです。彼のウスノロぶりのおかげで、私たちは何度も窮地に陥りましたね」
魔法使いが、甘い、毒の声で誘いをかける。
「彼さえいなければ、と何度思ったことでしょう」
魔法使いの言わんとすることを、少女は瞬時に理解した。
少女のように素手で怪物と渡り合う体術使いにもっとも求められるもの。
それは判断力の速さだ。
常に先陣を切って怪物の群れへ突撃する少女。
体をかすめる怪物どもの爪やくちばし。
一瞬のためらいが、即命とりとなる。
『君のおかげで、今回も血路が開けたよ』
戦いの後、勇者は必ずそう言って少女の肩を叩いたものだ。
消すのが魔法使いだろうが戦士だろうが、どちらでも良いのだ。
少女に迷いはなかった。
「まったくだな。私もそう思う」
少女と青年は視線を合わせて、ともに薄く笑った。
無言のうちに合意は得られた。
「それでは、戦士を消す具体的な方法を練るとしよ……」
最後まで言い切らず、少女が口をつぐんだ。
洞窟の入口で、人の気配がしたのだ。
戦士が見回りから戻ってきた。
「何も異常はない」
戦士はのっそりと焚き火の前に腰をおろした。
少女と魔法使いは、目を見交わした。
最初に、あまりにも長く無言の時を過ごしすぎた。
戦士消す具体的な方法は、まだ立てていない。
しかし、グズグズしていては戦士に怪しまれてしまう。
「では、また私が見回りにいくとしよう」
少女がスッと身軽に立ち上がった。
「いってらっしゃい」
「頼む」
後ろ髪をひかれながら、少女は洞窟を後にした。
少女と魔法使い、自分はどちらに付くのか?
優越感を覚えていた戦士だったが、見回りの最中、頭が冷えてきた。
自分は、どちらの味方になろうとしている。
すなわち、どちらかを裏切ろうとしている。
自分が裏切られる可能性はないのか?
自分は今まで散々楯にされてきた。
戦士という役回りは、表向きは戦の花形だが、実際は他人の尻拭いばかり。
華々しい斬り込み、多対一で敵を屠る、誰もが認める派手な戦果は、みな少女や青年が持っていってしまう。
これまで自分ばかりが損をしてきた、という思いは拭いきれない。
またもや、俺が貧乏くじをひかされる、俺が消されるのではないか……。
戦士は、そんな疑惑を胸の秘めて洞窟へ戻ってきた。
(おかしい……)
魔法使いと二人になった時に流れた微妙な空気を、戦士は敏感に感じ取った。
「さきほどの話の続きなんだが……」
内容を曖昧にぼかして、カマをかけてみる。
「あ、ええ、はい……」
魔法使いの、何とも歯切れの悪い返事。
やはり!
戦士は心の中で舌打ちした。
同時に、裏切られる可能性に気がついた自分の聡明さを褒めずにはいられない。
もし何も気付かず魔法使いにベラベラ喋っていたら、消されたのは自分に違いない。
洞窟内に、重い沈黙が落ちる。
どうするべきか……。
しばし逡巡した戦士だが、己の戦い方どおり、正面から切り込んだ。
「君が、あの女に騙されかけているのでなければよいが」
「私が騙されるですって?」
魔法使いが、ようやく精気ある反応を示した。
「ああ、あの女の狙いは金の独り占めだ」
戦士は声に抑揚をつけずにつづけた。
「俺はこの通り、頭の回転の悪い、もっさりした男だ。戦士仲間には“鈍牛”とバカにされていた。君みたいに頭の回転の鋭い切れ者が羨ましいと思うが、こればかりは生まれもったものだから仕方ない」
戦士が言葉に垂らしこんだ毒、すなわち褒め言葉に、魔法使いは自尊心をくすぐられた。
良い気持ちになることを抑えることができない。
「しかし」
戦士が語気を強めた。
「君の頭が良すぎるから、心配なこともあるんだ」
「それは一体なんです?」
高揚した気分に水を指され、魔法使いはムッとした口調になった。
「俺を消そう、そう話を持ちかけてきたのは、あの女からじゃないのかい?」
戦士はズバリと切り出した。
魔法使いは何も答えなかった。
青年の頭が猛烈な勢いで回転し、クセである親指の爪を噛み始めた。
戦士の言うとおり、自分の呟きを聞きつけ、話を持ちかけてきたのは少女からだ。
しかし、それにどんな意味があるというのだ。
戦士は何を言わんとしているのだろう?
戦士は無言で青年を見ていた。
その時、頭の中で閃いたものに、青年は鈍器で殴られたような衝撃を覚えた。
驚愕の表情で戦士を見る。
戦士はゆっくりと頷いた。
「さすがは君だ。どうやら気がついたようだな」
魔法使いは、驚きのあまり声も出ない。
「仮に君たちが協力して俺を消したとしよう。残るのは君たち二人だ。あの女の早い攻撃を、君は回避できるのかな?」
そのとおりだった。
体術を極めた少女の攻撃は、恐ろしく早い。
あの魔王すらも翻弄し、勇者が攻撃をするための隙を作り出したほどだ。
もし二人になった時、少女が邪心を抱いていたとしたら……。
自分は苦もなく、少女の素拳に胸板を打ち抜かれるだろう。
魔法の一言半句を唱えるヒマさえありはすまい。
少女の速さはそれほど絶対的だ。
「俺と二人で、あの女を消す。最初の計画通りに。それがもっとも良い作戦だと、自分は思うのだがな」
「たしか、に……」
魔法使いは苦々しげに頷いた。
危うく、虫も殺さぬような涼やかな顔をした少女に騙されるところだった。
「では、あの性悪女を消す具体的な方策を……」
そう戦士が言いかけたことろで、洞窟の入口に気配があった。
少女が見回りから戻ってきたのだ。
最初から、すぐに少女を消す方法に入っていれれば。
戦士は心の中で舌打ちした。
「何も異常はない」
少女はスタスタと歩いてくると、焚き火の前に腰をおろした。
「次は、私の番ですね」
青年は立ち上がると、キッと少女を睨んだ。
魔法使いの厳しい視線に、少女は一瞬たじろいだ。
「では行ってまいります」
「頼む」
戦士の言葉に見送られ、魔法使いは背中から怒りの気配を発しながら、洞窟を出て行った。
洞窟の中には、戦士と少女。
戦士は魔法使いに話をしている時、重大なことに気がついた。
自分が魔法使いと協力して少女を倒してしまったら……。
残るは自分と魔法使い。
青年の魔法は強力だ。
特に魔王直属の配下たちをことどとく灰にした炎は、世界最強と言っても過言ではない。
人間など触れただけでケシズミにされる。
いかに体力自慢、防御自慢の戦士とはいえ、青年の魔法だけはどうしようもない。
青年が、魔王金貨を独り占めせんと魔法を唱え始めたら、自分は太刀打ちできない。
一人を始末し、残る二人。
それは、自分と少女でなければならない。
戦士は短く刈り込んだ金髪をグシャグシャと掻き乱した。
これまでの人生、これほど頭を使ったことはない、というほどまで戦士は考えた。
考えに耽る戦士の様子を、向かい合って座った少女が、視線の定まらない表情でボンヤリと眺めていた。
先ほど、魔法使いが自分を睨んだ目つきが気になっていたのだ。
焚き火の火勢が弱まり、少女が追加の薪を投げ込んだ頃、戦士の考えがまとまった。
戦士はずるそうな目で、自分よりずっと小さな少女を見上げるように口を開いた。
「さっき魔法使いが出て行くとき、君を睨んだ目つきを見たか?」
「あ、ああ」
考えていたことをズバリと口にされ、少女は狼狽した。
「ヤツは君を恨んでいる」
「ど、どうしてだ?」
「ヤツは魔王を倒す時、雑魚ばかり自分に任せて、魔王への名誉ある最初の攻撃をした君を逆恨みしているのさ」
「そんなバカな!」
少女はガバリと立ち上がり、拳を握った。
「私は最も危険な切り込み役を務めたんだぞ!」
戦士に掴みかからんばかりの勢いで少女が口泡を飛ばす。
「それはみんな分かっているさ」
戦士はひと呼吸おいてつづけた。
「魔法使い以外はな。しかしヤツは陰険な嫉妬屋だ。自分はいつも安全な位置で、策略を巡らすのが大好き。そんなヤツに、我々危険な最前線に立つ人間の気持ちなど分かりはしない」
「くそッ!」
少女は片膝をつくと、地面に拳を打ち込んだ。
「あいつ、そんなことを腹で考えながら、涼しい顔をしてッ!」
最後のほうは言葉にならなかった。
目の前に戦士がいる。
自分だって、戦士を消すことに、一時は賛同したのだ。
一方的に魔法使いを責めることができないのは分かっているのだが……。
だからといって、少女の腹立ちが収まるわけではなかった。
「問い詰めてやらなきゃ気がすまないッ! アイツ、帰ってきたら締め上げてやる」
「まあ、待て」
戦士が憤る少女を宥めた。
「問い詰めたところで、あの狡賢い魔法使いが、素直に腹を割るもんか。それより、ここは俺たち二人が協力してヤツを……」
その時、洞窟の入口で人の気配がした。
魔法使いが、見回りから帰ってきたのだ。
戦士はあまりにも長く考え込み過ぎた。
もっと早く少女を焚きつけることができていれば……。
「何も異常はありませんでした」
魔法使いは少女と視線を合わせないようにしながら、焚き火の前に腰をおろした。
少女は縄張りを荒らされた猫のように、全身から怒り気配を発している。
「次は俺か」
戦士は重々しく立ち上がると、洞窟を出てった。
自分が戻ってきた時は、魔法使いが死体になっていることを確信しながら。
洞窟に残った魔法使いと少女。
お互いに爆発寸前だった。
それでも、魔法使いはやや冷静だった。
魔法使いは、戦士が戻ってこないことには、少女を倒せないのだから。
少女が痺れを切らし、立ち上がる。
「貴様のような根性曲がりの陰険野郎は、もっと前にくたばっておくべきだったんだ」
少女の剣幕に、魔法使いは飛び退って、洞窟の壁面に背をつけた。
「なぜアナタが私に対して怒るのです?」
「うるさいッ!」
少女は聞く耳を持たなかった。
魔法使いの頭脳が、恐ろしい速さで回転を始める。
なぜ少女が自分に怒りを感じているのかは分からない。
しかし、ことは緊急だ。
理由を追求しているヒマはない。
自分も少女に怒りを覚えている。
しかし、少女の感情に自分の感情をぶつけても火に油だ。
では『理』で説き伏せるか?
いや、もう少女は理を聞く耳など持っていない。
残されたのは『利』だ。
「ま、待ってください、私を殺してもいいんですかッ?」
「死ねッ!」
焚き火を踏み越えて迫ってくる少女に、魔法使いは顔面蒼白で叫んだ。
「アナタは利用されているんですよ。戦士はあなたを殺すつもりなんだッ!」
少女の歩みが、ピタリと止まった。
そして、池に投げ込まれた炎のように、急激に怒りが冷めていく。
少女は、魔法使いの絶叫で、瞬時に理解してしまったのだ。
一対一では、自分は戦士に勝てないことを……。
少女は虚ろな表情になり、元の場所へ戻るとへたり込んだ。
両腕でヒザを抱きかかえるように丸くなる。
自分は一撃必殺の拳を持っている。
たとえ魔王とて、急所さえ突ければ大ダメージを与える自信がある。
しかし……。
それとて、他者が急所をさらけ出すよう、隙を作ってくれてこそだ。
全身を特別製の鎧で覆った戦士に急所は無い。
魔王を倒したことで、名実ともに世界最強となった戦士が防御に徹すれば、鎧越しに致命傷を与えることは不可能だ。
もちろん、戦士の鈍い攻撃が、自分に当たることなどないだろう。
しかし、長びけばどうなるか?
致命傷を与えられない以上、長期戦になるのは必至だ。
ただ防御に徹すればよいだけの戦士と、常に動き回らねばならない自分。
少し疲れたところに、戦士の剣がかすっただけでさえ、自分の動きは止まる。
動きが止まれば、後は大人と赤子の喧嘩だ。
(自分は、騙されているのだろうか……)
少女は、丸くなったまま動かない。
魔法使いはここぞとばかりに、少女をかきくどく。
「そもそも、アナタはいつももっとも強い敵に特攻。私は大量の敵を常に相手にしなければなりません。二人とも危険な橋ばかりです。その点、戦士はいつも私たちが討ちもらして、弱った敵のトドメばかり。世の中、あんな楽な商売はありはしませんよ」
魔法使いの甘言も、少女が興味を示さないのではつづかない。
やがて、静寂が洞窟を支配した。
少女が、ふと自分は捨て子であったことを洩らした。
少女の生い立ちは、勇者にさえ秘密にしていたことだった。
魔法使いが相槌を打つ。
そこから青年が少女を焚きつけ、戦士を消す具体案に移りかけたところで時間切れとなった。
戦士が戻ってきたのだ。
戦士は、魔法使いが死んでいないことに内心驚きつつも、平静を装った。
「何も異常はない」
「では私が行こう」
少女が立ち上がった。
少女の表情には、何が何でも、どんなことをしてでも自分だけは生き抜く、という決意が現れていた。
少女が魔法使いを消していると期待してやってきた戦士は、何事もなかったような空気を敏感に感じ取り、自分の作戦が失敗したことを悟った。
がっかりすると同時に、窮地に立たされたことを知る。
魔法使いがどんな策を弄したのかは分からない。
しかし、こうして生きている以上、今度は自分を消す方向で話がまとまったに違いない。
なんとかして魔法使いが自分を殺さないよう、説得せねばならない。
「君があの女に、うまく丸め込まれたんでなければよいが」
戦士はドサリと腰を下ろすと、ぶっきら棒を装って言った。
「なんのことです?」
「あの女は、体術自慢で、自分を切れ者だと思ってる。幼い顔に似合わず、人を垂らしこむのも上手い」
戦士の口調は、次第に熱を帯びてきた。
「あの女はこんな提案をしていたよ。二人で君の計画を聞きだして、その裏をかこう、とな。反対するのもおかしいんで、俺は承知したふりをしておいた。しかし、俺はこの通り鈍重でお人良しの戦士だ。こうして君に喋ってしまう。それに俺と君は最良の相棒だ。君の強力な魔法でも倒せなかった敵に、俺がトドメをさす。何か時にあの女と組まされた時は、あの女がさっさと行ってしまうんで、君は苦労したんじゃないかな」
戦士の熱弁に、青年は曖昧な相槌を打つ。
戦士の言うことは胡散臭いが、かといって少女を信じる気にもなれない。
なぜ、少女は勇者にも秘密にしていたという生い立ちを、自分に話したのだろう?
少女の生い立ちには同情すべき点がある。
もし、今以外の時に、生い立ちの話をされていれば、青年は少女に同情し、より親近感を覚えていただろう。
不幸な境遇の少女を助けてやらねばならない、と思ったに違いない。
しかし、よりにもよって、なぜ今?
同情させよう、懐柔しようという意図ではなかったか?
他人の可哀相な境遇に、素直に同情できないのは痩せた感性だとは思う。
しかし、今は場合が場合だ。
精神的にギリギリのところで、まさしく生死を賭けた戦いを繰り広げているのだ。
ここで不用意に相手へ同情するのは、優しい人ではなく、単なる愚か者だ。
「私は魔法学院を追放された魔法使いでしてね」
青年が、ポツリと漏らした。
「学校内の醜い派閥争い、実際の魔力も無いのに、理論にばかり傾倒する愚かな先生と同門たち。私はそれが嫌で、ひとりでコツコツ魔法の研究を続けていたのです。ある日、突如言い渡されました。『お前は危険分子だ。学院を追放する。以降、魔法を使ってはならぬ』と」
戦士の同情を買おうと思ったのではない。
鬱々と考え続けていて、つい口から出た独白だった。
「途方に暮れました。街頭で辻占い師をしながら細々と生計を立てていた私を拾ってくれたのが勇者でした。各国の王とも互角に渡り合える勇者のおかげで、私は再び自由に魔法を使い、研究できるようになったのです」
戦士は無言で青年の話に耳を傾ける。
静かな洞窟内で、焚き火の炎だけがゆらゆらと揺れた。
「まだ、まだです。魔王は倒しましたが、私はまだ自分を追放した魔法学院の連中を見返してはいない。私の研究が正しかったことを、連中に思い知らせるまでは、私は死ねない」
「君は生きるということがよく分かっている」
戦士は猫なで声で囁いた。
前後の見境いを無くして、青年が戦士を消してしまう危険は去った。
理性を失くして自分を消せば、少女に消されるのは自分だということを、青年はよく理解しているようだ。
とりあえずの窮地は脱した。
それだけでも、戦士には成功と言えた。
洞窟の入口で、人の気配がした。
少女が見回りから戻ってきた。
戦士の熱弁と、青年の独白に、あまりに時間を要し過ぎたようだ。
「何も異常はない」
少女はそう告げると、焚き火の前に腰をおろした。
代わって魔法使いが立ち上がる。
「では、私が見回りに行かせていただきます」
青年の声に精気がない。
「頼む」
「気をつけて」
戦士と少女が、魔法使いの背中に声を送った。
「魔法使いのヤツ、ずいぶん呆然としていたな。何かあったのか?」
焚き火に新たな薪をくべながら、少女が聞いた。
その声には落胆の色が隠せない。
魔法使いが戦士を消していることを、少しは期待していたのだ。
やはりそれほど甘くはない、と少女は痛感した。
黙り込みがちになる戦士と少女。
だが、戦士はじっとしているわけにはいかなかった。
戦士にとって最良の結果を得るには、少女に魔法使いを消してもらわねばならない。
なんとか、少女を焚きつける材料はないものか……。
戦士は頭を回転させる。
「魔法使いのヤツ、すべて俺に打ち明けたぜ。話を合わせ、その裏をかこうという作戦がどうのこうのと……」
少女はフウンと気のない返事をし、内心、戦士の頭の悪さに呆れた。
もうとうに心の底は見透かされているのだ。
今さら、どう言い繕おうとも、言葉で人を動かすことなどできはしない。
この鈍くさい男を消してやりたい、と少女は思ったが、それは無理なのだ。
一対一では、この男には敵わない。
自分ひとりの力では、どうにもならない。
少女は、頬に自虐的な笑みを浮かべた。
ツラツラと魔法使いの悪どさを言い連ねていた戦士だが、少女の反応が芳しくないため、やがて押し黙ってしまった。
人を見下したような笑みを浮かべている少女を見て、胸が悪くなる。
この小賢しい女を消してやりたい。
消してしまう実力も、自分にはある。
しかし、それはできないのだ。
力で物事を解決することの多かった戦士にとって、この状況は地獄だった。
やがて戦士は、金髪をモシャモシャと掻き回しながら、鬱々とした表情でこぼし始めた。
「みんな、みんな騎士見習いの連中は俺をバカにしていたんだ。やれ足が遅い、剣の振りが鈍いと、鈍牛、鈍牛、と訓練のたびに囃し立てた。戦場に出たことも無い、騎士になっても後方でふんぞり返っているだけの貴族のお坊ちゃんどもに」
戦士には、目の前の少女の姿も目に入っていなかった。
「戦場で武勲を立てても、手柄はすべて安全なところでふんぞり返っていただけの坊ちゃん騎士どもに持っていかれる。当たり前だ。戦場の戦果を上に報告するのがヤツラの仕事なんだからな。ある日、俺はとうとう我慢できずに、戦場で後ろから坊ちゃん騎士に斬りかかろうとした」
戦士はひと呼吸おいてつづけた。
「それを止めてくれたのが、連合軍として同じ隊に加わっていた勇者だった。勇者は言ったよ。『ずっと君の勇猛な戦いぶりを見ていた。ここで将来を棒にふっちゃいけない。俺と共に正義のために戦おう』と。俺は涙が止まらなかった。誰も気にもしていないと思っていた俺の戦いを、勇者はずっと見ていてくれたんだ。否も応もなかった。俺は軍を離れ、勇者の仲間になった。だからこそ」
最後は涙声になった。
「死んだ勇者のためにも、俺はここで死ぬわけにはいかない。何が何でも生き抜かねばならない」
「オマエの言うとおりだ」
少女は静かに相槌を打ち、内心ホッとした。
戦士の涙ながらの話に、心を打たれたわけではない。
突発的に戦士が自分に襲いかかってくることは無さそうだ。
そのことに安堵したのだ。
鈍くさい戦士さえ暴走しなければ、当座自分の安全は保障される。
戦士の泣き言のような話に、静かに相槌を打ちつづける少女。
やがて、洞窟の入り口で人の気配がした。
魔法使いが見回りから戻ってきたのだ。
「異常はありませんでした」
「では俺が行こう」
戦士は立ち上がって洞窟を後にした。
「いってらっしゃい」
「気をつけて」
残された少女と青年は、うろん気な視線で戦士を見送った。
洞窟へ戻ってきて、奇妙な空気を感じ取った魔法使いは、苦い薄笑いを浮かべた。
「私がいない間、さぞかし戦士にまた、色々と掻き回されたことでしょうね……」
「まあ、な」
少女は曖昧に答える。
両者とも、あまり強いことも言えない。
どちらもが、戦士と組んで目の前の相手を消そうと提案したこともあるのだ。
あまり会話の弾まない二人にできることは、この場にいない戦士をけなすことくらい。
「だいたい、戦士なんて最初から仲間に加えなくても、魔王は倒せたんですよ。いつだって私たちの窮地は戦士から。彼には等分の報酬を得る資格なんてないんです」
「そうだ。アイツの足が遅いせいで、なんど俺たち一行が逃げ遅れて、不要な戦いをしなけりゃならなかったことか」
二人は話し合う。
しかし、内容は愚痴の域から出はしない。
気が乗らないし、乗るはずもない。
目の前の相手は、消してしまいたい対象であると同時に、自分の命を保つ命綱でもあるのだから。
「いずれにせよ、あいつはひねくれたヤツさ」
結論はいつもそこへ行き着く。
金のために、互いに命を預けて戦った仲間を消す。
考えてみれば、最初の頃は純粋な殺意がギラギラとみなぎっていた。
心とろかす、禁断の木の実のような甘い、それでいて、燃え上がらんばかりの刺激だった。
大金を得るために、生き残るために、全精力を注ぎ込んで素早く作戦を練り、ぎりぎりの神経戦を繰り広げる。
それは、魔王を倒した時に感じたカタルシスをさえ上回る、最高に価値のあるゲームだった。
しかし、今はどうだろう。
燃えあがらない。
燃えあがるはずもない。
それは、料理の鍋の沸騰を待つ気分にも似ていた。
永遠に熱々にはならない料理を待つ気分に……。
絶対に来ることのない満足感が、深い闇をいつまでも覆っていた。
いったい、何度見回りを交代した頃だろうか。
「おい、出てきてみろ」
見周りに出ていた少女が戻ってきて、洞窟に残っていた戦士と魔法使いへ告げた。
三人は揃って洞窟を出た。
外は、いつの間にか白み始めている。
魔王を倒して、最初の朝がやってきたのだ。
ずっと下を道を、ボロを纏った人間たちが列をなして歩いている。
「魔王城で奴隷になっていた人間たちだ。彼らから聞いた。怪物の残党たちはみな魔界へ引き上げたそうだ」
少女が説明した。
三人は無言で頷きあうと、揃って洞窟へ戻った。
魔法使いが、焚き火のそばに置いてあった魔王金貨を取りあげる。
青年は三枚づつを戦士と少女に渡し、自分も三枚を懐にしまった。
「私たちはいい仲間でしたね」
魔法使いが、灰色に濁った目で言った。
「ああ」
戦士が死人のように精気の無い声で同意する。
「お互いにけっして裏切ることはなく、最後まで信頼できる、そんな関係でした」
「そうだな」
少女が、口元にニヒルな、嫌らしい笑みを浮かべて相槌を打った。
「この一枚は……」
魔法使いは残った魔王金貨一枚を死んだ魚のような目で眺めると、洞窟の外に向かって歩き出した。
戦士と少女もつづく。
魔法使いは、切り立った崖へ向かって歩いた。
崖の突端へ、そっと魔王金貨を置く。
戦士は無言で腰から剣を、自身愛用の大剣ではなく、やや小ぶりな剣を抜いた。
勇者が自己犠牲の呪文を唱える際、三人に残した剣だった。
戦士は勇者の剣を逆手に持つと、剣を思い切り地面に振り降ろした。
剣は魔王金貨ごと、深々と地面を貫いた。
飾り気のない勇者の剣が、崖の上、朝の陽光を浴びてギラリと光る。
それは、今は亡き勇者の墓標だった。
「最後の魔王金貨は、世界を救った勇者、あなたの取り分です」
「魔王を倒してしまったから、俺たちはお払い箱になる。そんなことも考えたんだが……」
戦士が低い声で言った。
三人は、これから再びドロドロとした思惑渦巻く人間社会へ戻る。
勇者たちの一行は、常に世界中の人々から称賛されてきた。
一方、それを嫉み、僻み、足を引っ張ろうとする者も、けっして少なくなかった。
以前は、そんな嫉妬にかられた人間など、三人は相手にしなかった。
悪の魔王を倒して、世界に光を蘇らせる。
光輝く理想が、三人の胸をいっぱいにしていた。
反面、心のどこかで、自分たちを嫉む人間を、高邁な理想を理解できない愚かな人間だ、思っていなくはなかった。
今は違う。
欲望、嫉妬、打算、裏切り。
そうしたものが混沌となってこそ、自分の安全は保障されるのだ。
純粋すぎる行為など、結局、自分の首を絞めているだけに過ぎない。
身動きできない混沌こそ、最高の安全地帯。
「もしかすると、魔王の存在さえも……」
そう言いかけて、魔法使いは口をつぐんだ。
勇者の墓標の前、顔を見合わせた三人の表情には、この洞窟に駆け込むまでにはみられなかった苦い、老成した笑みが浮いていた。